学習机市場の近年の動向を一言で言えば「多様化」。少子化によって市場が縮小し、メーカー間の競争が激しくなったのと、消費者のライフスタイルや価値観も様々になったためです。そのため、学習机と一言で言っても昔に比べると色んなバリエーションがあり、なかなか絞り込むのが難しくなっています。
というわけで、家具メーカー出身で、特に学習机にはウルサイ学習机評論家の収納マンが、学習机選びのコツをお教えしましょう!
[1] スタイル
昔ながらの学習机らしいスタイルがメインである一方、最近は様々なスタイルがあります。使い勝手やレイアウトにも大きく影響しますので、非常に大きなポイントと言えます。
個人的にはシンプルなベーシックデスクがオススメですが、リビングに置く場合はユニットデスクや天板昇降式デスクも良いと思います。リビングから子供部屋に移動することを念頭に置いて組み合わせデスクを選択するというのもアリでしょう。逆に、学習環境の良くないライティングデスクやベッド下収納式のデスクはあまりオススメできません。
ベーシックデスク
一般的な上棚付きの学習机で、棚の背が低いロー棚タイプと、棚の背が高いハイ棚タイプに分かれます。近年はハイ棚は圧迫感がある、予算が高くなるなどの理由から敬遠されがちで、ほとんどなくなってしまいました。ロー棚も同様の理由から以前と比べると少なくなっている印象です。
上棚があると必要な教科書類を手近に置けることがメリットです。収納力もあります。一方で、天板面が狭くなるというデメリットがあります。
ユニットデスク
もともとユニットデスクは現在で言うところのセレクトタイプ(デスク、ワゴン、棚などの組み合わせを選べるタイプ)を指しましたが、近年は書棚をデスク側面に配置したものを指すことが多くなっています。
書棚をデスク側面に配置したユニットデスクのメリットは、普通に書棚を正面を向けてレイアウトするよりも省スペースであること。また、上棚同様に教科書類に手が届きやすいのもメリットです。一方で、書棚上段の奥や足元の本に手が届きにくいのがデメリットと言えます。
組み替え式デスク
組み替え式デスクは書棚とデスクがセットになったもので、配置や組み換えによって3~10通りのレイアウト変更が可能となります。
メリットはオールインワンでコスパが良いこと。また、ライフスタイルの変化に応じてレイアウトを自在に変更できるところです。一方で、余計なものが付いていて無駄が多いと感じる、いかにも学習机っぽくて無理と言う声も聞かれます。
天板昇降式デスク
現在の学習机の多くは椅子の座面の高さを調整することで大人が使うのと同じ天板高のデスクを使います。対して天板昇降式デスクはデスク天板の高さを調整することで子供の成長に合わせます。
そのメリットは子供の足が床にベタッとつくため勉強に集中できること。また、天板高が低いので見た目の圧迫感が少ないことです。一方で、ワゴンの収納量が少なくなりがちなのと、天板高の調節が大変なことがデメリットと言えます。
ライティングデスク
一般的にライティングデスクは天板がフラップ扉のようになっており、上部に棚が設けられています。また、幅は75~90cmのものが多くコンパクトです。ただ、近年はまったく流行らず、取り扱っている学習机メーカーはわずかです。
メリットは設置スペースが少なくコンパクであること。一方のデメリットは、受験勉強などで広い天板が必要になる頃には役不足であること。また、見た目に圧迫感が強いのも敬遠されるところです。
ベッド付きデスク(システムベッド)
ベッド付きデスクは学習机とベッド、商品によってはチェストなどもセットになった商品。組み合わせを選べるものもあります。基地のようなので子供にも人気があり、ニーズは底堅いものがあります。
オールインワンで省スペース、コスパも良いと思われがちですが、実際にはむしろレイアウトが難しく、品質の低いものが組み合わされていることがほとんどでコスパが悪いです。一方で、子供が喜んで机に向かってくれるという期待が持てます。
[2] メーカー
大きく分けてオフィス家具メーカー系と家庭用家具メーカー系とに分かれる業界構造ですが、いったいどういうメーカーがあって、それぞれどういう特徴があるのか、以下の表にまとめてみました。
予算に問題がなければ、高級家具メーカーである浜本工芸やカリモク家具が素材や品質が良いのでオススメですが、学習机トップシェアのコイズミファニテックや、学習机のパイオニアであるイトーキなども安心して使っていただけると思います。
コイズミファニテック
コイズミファニテックは学習机メーカーとしてトップのシェアを誇ります。ラインナップも豊富で、機能的な組み替え式デスクを主力としつつも、「ビーノ」のような現代のライフスタイルにマッチした学習机も展開しています。また、照明器具の小泉産業グループであることもデスクライトでアドバンテージを持っていると言えるでしょう。
イトーキ
イトーキは学習机のパイオニアですが、現在は島忠ホームズを除いて家具販売店とは縁を切り、ネット販売にシフトしています。品質はコイズミファニテックと同等のものが多く、それでいて中間マージンを省いた価格が魅力となっています。
くろがね工作所
くろがね工作所は以前は大手ブランドという位置付けでしたが、近年は主力プレーヤーとは言えません。天然木を使ったデスクも扱っているものの、主力はカラーデスクです。
ヒカリサンデスク(光製作所)
光製作所は座椅子など和家具や公共施設や店舗向けのコントラクト家具に強い家具メーカーです。その学習机ブランドであるヒカリサンデスクは昭和の時代にテレビCMを放映していたこともあり、熟年層には認知度が割りと高いです。近年は天然木を使ったシンプルなデスクが多いです。
大商産業(金次郎デスク)
近年、学習机市場の影の帝王と言えるのが大商産業です。金次郎デスクのブランドでも販売していますが、店頭ではほとんどその名前を出していません。カラーデスクを主力としており、ニトリなどでも扱われています。価格は大手ブランドより安いです。
一生紀
近年、手頃な価格と豊富なラインナップで人気を集めているのが一生紀(いっせいき)です。天然木の質感が伝わるシンプルなデザイン。ベトナムの自社工場で作ることでコストを抑えています。
カリモク家具
カリモク家具は総合家具メーカー最大手。ライフスタイル提案型の商品づくりがうまく、消費者から高く評価されています。デザインがとてもシンプルで美しく、品質も申し分ありません。ただし、割高感はあります。
浜本工芸
浜本工芸は皇室に献上したということで家具メーカーの中では一躍トップブランドになりました。値段は立派ですが、天板のナラ無垢は最上級と言えるもので、引出しの開閉は婚礼箪笥のようにスムーズ。品質ではピカイチと言えるでしょう。
堀田木工所(hotta woody)
堀田木工所はアルダー材にオイル塗装を施すことで、国産ながら価格が手頃なことから人気となっています。基本的に質感や色味が同じなので、様々な組みあわができるのも魅力。店舗オリジナル商品がとても多いです。
杉工場
杉工場は堀田木工所と同様にオイル塗装のアルダー無垢材を使った学習机が主力です。洗練されたデザインで一時は堀田木工所を駆逐するかと思いましたが、近年は割高感があって人気に勢いが感じられません。
[3] 素材
家庭用家具メーカーの学習机に注目が集まった2000年頃は猫も杓子も最高級家具用材であるナラやオークの無垢材に人気が集まりましたが、近年は無垢ではなく突板、もしくはアルダーなどのコストを抑えた材にシフトしています。また、MDF合板を使ったカラーデスクや、メラミン化粧板のデスクも多くなっています。
集成材(無垢)
天然木を継ぎ合わせて一枚の板にしたもの。大きな角材を繋ぎ合わせた幅ハギと、小さな角材を継ぎ合わせたフィンガージョイントが一般的で、幅ハギのほうが美しく高価とされる。
パイン
パイン(松)は軟らかくてキズがつきやすく、割れたり反ったりすることもあり、また節が多くて凸凹が生じやすいため、近年は学習机の天板に用いられることはほとんどありません。ただ、パイン独特の風合いを好む人もいます。
ラバーウッド
ラバーウッド(ゴムの木)はゴムの搾りかすを再使用したエコ素材です。木目はほとんどありませんが、比較的硬くてキズがつきにくいことから、現在もメジャーな木材のひとつです。
ナラ、オーク
ナラやオークは木目が美しいことと硬さが十分であることから家具用材として重宝されています。虎斑(とらふ)という模様があるものが本来は高級品ですが、気持ち悪いと言う人もおり、現在は避けて使用される傾向です。
アルダー
アルダーは木目が穏やかなことで近年人気があります。オークなどに比べるとやや軟らかいものの、加工しやすく、価格が手頃なのがメリットと言えるでしょう。
ウォールナット
リビングダイニング家具と同様に近年は学習机でもウォールナットの人気が高まりつつあります。ただし、非常に希少な木材なので価格は高いです。
ヒノキ
ヒノキは木質感や香りが良いことや、国産材利用促進の観点から、学習机でも使われるようになりました。ただ、軟らかい木であるためキズが付きやすいです。
突板
突板(つきいた)と言う場合、天然木を薄くスライスしてフラッシュ合板やハニカム構造の合板に貼り付けたものが一般的です。ハニカム構造とは、ハチの巣状にした厚紙を合板の間に挟んだもので、強力なダンボールのようなもの。
MDF(中繊維合板)
MDF(中繊維合板)は木クズを繊維状にして接着剤で固めたもの。強度は十分で、エコな素材と言えます。学習机の天板としては、以前は塩ビシート(PVC)を貼り付けたものが多かったですが、近年は技術の進歩により木目などを直接印刷できるようになりました。
メラミン化粧板
年は木質感のあるデスクが好まれる一方、ウッドショックなどで木材の価格は高騰しています。また、子供が使うものですから手入れがしやすいもののほうが良いに違いありません。そういった背景から木目調のメラミン樹脂シートを貼ったデスクが増えています。
強化プリント紙
学習机の天板に普通のプリント紙が使われることはよほどの安物でない限り最近はありません。多くは強化プリント紙と呼ばれるもので、メラミンほどではないにせよキズや汚れに強いです。質感は天然木と見紛うものもあります。
ちなみに、木の素材も大事ですが、塗装も重要です。近年は塗装はウレタン樹脂塗装が一般的ですが、オイル仕上げ(自然塗装)のものもあります。たとえばアルダー材の場合、ウレタン塗装にすればツヤが出て木質感は若干失われますが、表面硬度は鉛筆の芯に負けない程度になる一方、オイル仕上げは質感が良い一方でキズが付きやすく汚れやすくなります。また、定期的にオイルを塗り込むなどメンテナンスが必要になります。個人的には、学習机を道具として見る場合、オイル仕上げはあまりオススメできません。
以上、スタイル、メーカー、素材について見てきました。続いては、価格面、購入時期などについてお話したいと思います。

関連記事

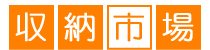




























コメント